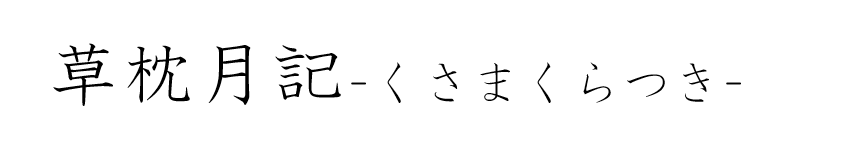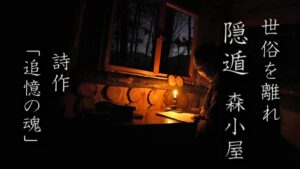東京からの客人が帰路についた。とても気持ちのいい客人だった。大都会で仕事をし、妻帯する身でありながら、老荘思想を深く読み、体験と智慧を重んずる男だった。
突拍子のない話だが、男の話を聞いて、犬を飼いたいと心底思った。犬といっても、現代にあるような、ただ室内で愛でるペットとしての犬ではない。ペットとしての犬もたしかに可愛いが、ただ愛でて、写真を撮って、家族の一員だというのは、どこか自己愛に似た偽りを感じる。
もともと、犬との関係にも文化はあった。人間と犬の歴史は、さかのぼれば狩猟に行きつくという。食い扶持をつなぐために、主従は一体となり狩りに出た。犬は猪の匂いをかぎつけると山のなかを突き進み、猪を見つけると、そのまま追われる形で、猟銃を持つ主人のもとに連れてくる。失敗すれば、犬は猪にやられるし、主人もまた、猪と対峙するため命がけである。だが、そうして共に命を張るのだから、人間と犬との絆は今よりもずっと深いものだった。
お手や、お座りや、待て、といった躾にも、文化的な意味があったにちがいない。小泉武夫氏の「猟師の肉は腐らない」という小説に登場する、義っしゃんという猟師は、猟犬に「石!」という躾をしていた。これは「石になれ!」という意味で、獣に気配を悟られないための躾である。無論、すべての犬が猟に出るわけではないが、怪しい人間が敷居を跨ぐと、吠えたり噛みついたりして、主人を守ろうとした。主人のために命を張る犬は健気で、可愛く、美しく、だからこそ人間は、犬を可愛がってやらんくてはならなかったんじゃなかろうか。
2024.11.4