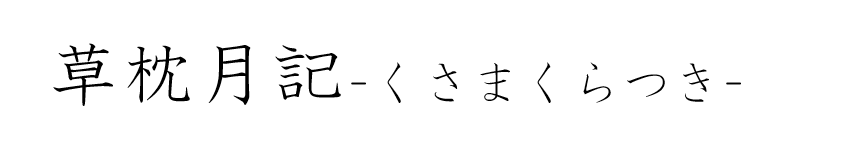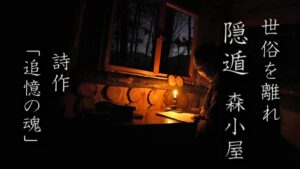この現世における生活は、それ自身において、それ自身によって、一つの目的になりえないことを認めるとともに、この現世においてわれわれ人間は苦悩を通して学ぶものである。現世における人間の生活は、何かより大きな全体の一つの断片にすぎないのであり、このより大きな全体においては、人間の魂の精神的風景の中心的な支配的特徴は、人間の魂の神に対する関係である、としている。
蝋山政道「トインビー史学と現代の課題」
諏訪地域は雪があまり降らない代わりに、諏訪湖が全面凍結するような氷の世界である。凍った諏訪湖に亀裂が生じると山脈のようにせり上がる。これは「御神渡り(おみわたり)」と言って、諏訪大社の神様である建御名方命(たけみなかたのみこと)が、湖の反対側に住む八坂刀売命(やさかとめのみこと)に会いに行くために氷の上を歩いた跡とされる。地元の人間は、これを神様の愛の物語として深く信仰した。
また諏訪地域では、寒冷な冬に作物が育たないことと、山に囲まれ自然が豊かであることから狩猟文化が発達した。毎年、諏訪大社では、御頭祭(おんとうさい)といって、鹿の頭が生贄として捧げる(もっとも今日は剥製が使われるらしいが)祭事が行われる。仏教の影響で肉食が忌避された時代も、鹿食箸(かじきばし)といって鹿肉を食べることの赦される免罪符が与えられた。
私が猟師になろうと思い立った地は、諏訪湖という信仰の湖があり、狩猟文化を崇めていた。この偶然を仕合せなことと思う。西洋化した社会では、生活の一挙手一投足が、全体の一部として営まれることは容易ではない。仕事は仕事、家事は家事であり、それ自身が自己目的として完成している。完成ゆえ安定するが、いくら安定しようと「生」の回し車を永遠と漕ぎ続けることに魂は不安を抱くものだ。
われわれは、生かされているという感覚を取り戻す必要がある。仕事にしても家事にしても、与えられた役割に対して殉ずる勢いで打ち込むことで、大きくなりすぎた「自分」という主語は身の程をわきまえ、本来そこにあるべき全体と繋がりを持つようになる。
今日、私が心がけることは、今ある役割を真に全うすることである。新聞配達という、小さな小さな役割であるが、私はこれにも誇りを持って取り組むのである。
2025.3.4