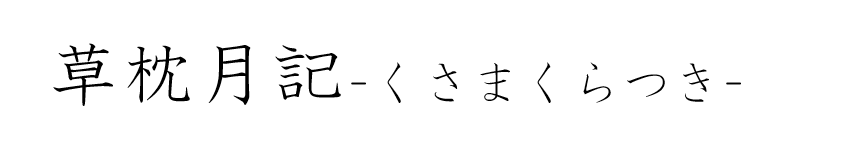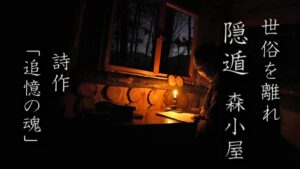友人の新聞記者が、社内のワープロでうっかり「百姓」と入力しようとしたところ、「次の言葉に言い換えなさい」と警告が出て、農家、農業者、農業経営者、農民などの言葉が例示されると言う。事態はここまで来ているのである。
宇根豊「国民のための百姓学」
百姓という言葉には、庶民ながらも立派に生きる、人間としての矜持がある。歴史のなかで流された、血と汗と涙の昇華である。昨年から畑で働いていると「就農」という言葉をよく耳にする。農に縁のなかった人間が、新しく農家として開業することを言うが(厳密には雇用就農といって、雇われとして働く形もある)、私はこの言葉がどうも好きになれない。為政者がキャンペーンとして打ち出すための作意が見え透いているからであろう。都会を出しにしながら、自然豊かで健康的な田舎暮らしをしようというヒューマニズムに乗っかった言葉にも聞こえる。
就農で農業従事者になることはあっても百姓になることない。思想が言葉を書き換えている。人間の矜持に満ち満ちた百姓という言葉は、近代合理主義によって陰に追いやられた。悔しいが、夏目漱石の「草枕」や島崎藤村の「夜明け前」を読んでいても、分からない言葉ばかりである。きりがないが、辞書で調べて本に書き込む。同じ日本人であるはずなのに、平成生まれの私には西洋文学のほうが読みやすい。日本人の矜持の詰まった昔の言葉は使われぬ、思想とカタカナで覆われる時代で育った。
とはいえ、日本人は日本人だ。その自覚を肚の底から紡ぎ出して、ほんの小さな心の隙間から入り込もうとする絶望を、心の外に追い出して生きるだけである。さあ、踏ん張ろう。
2025.3.2