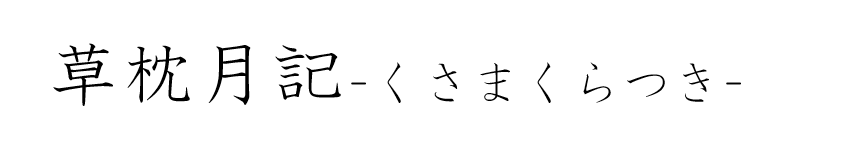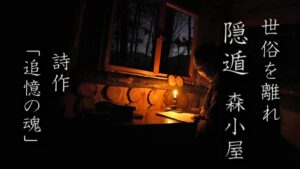家づくりがひと段落したので、珍しい形をした木でランタン台をこしらえたり、赤松の枝を用いて上着を引っかけるハンガーをつくったりしている。なるべく原形をとどめた荒々しい状態で、実用形式に落とし込んだものに美しさを感じる。ツリーハウスはその一例であるし、極端な話、洞窟に棲むことに密かな憧れを抱く男は、私を含めて世に一定数はいることだろう。
原形をとどめた状態は不安定であり、人間にとって不便なばかりでなく、恐怖を植え付ける存在となりうる。つまり、信仰の対象となる未知や自然への畏怖だが、物質文明には勝手が悪い。商品として生産するには、規格がばらばらである以上、品質が安定せず再現性が低い。効率性や実用性を追求すれば、不安定な原形は破壊され、安定した状態に加工するのがいちばんだ。
その点、食肉加工と似ている。豚や牛を丸ごと見れば、怖ろしく不安定で素直に食べようと思えないが、ロースやバラに切り分けられた状態であれば、何の抵抗もなく美味しく食べることができる。
再現性が高ければ、知識や技術の発展の土台となる。物質文明はそうして力を得た。人間である以上、おとぎ話に出てくるような、ドワーフが棲むような自然の家に憧れがあっても、快適で安全な家で肉体を大事に守るようにしたのが現実の家である。

現実を乗り越えて理想を体現を試みるも、現実の壁に突き放されるのが青年の宿命ではなかろうか。私は堕ちる形で現実から弾き出された力のない人間であったが、土竜のように地中を這いながら、壁の下から一つの理想に辿り着いたように思う。それがいいのか悪いのかは知らぬ。私は自分を駄目な人間だと認識している。ゆえに、再び立ち上がろうと足掻く日々である。
2025.2.19