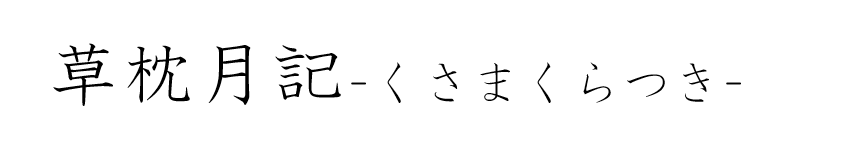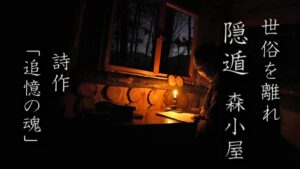私たちは、人間の手の入らない「原生自然」を一番価値のあるものだと考えている。また人為は、自然と対極にあるものだと位置づけている。しかし、これは明治時代に生まれた「誤解(新しい定義)」なのである。
宇根豊「国民のための百姓学」
私は森に棲んでいる。「住む」ではなく「棲む」と書くのは、自分も自然の一部であるという自覚からである。人が主と書いて「住」である。木を妻(ねぐら)にすると書いて「棲」である。鳥や獣とちがって、私は木の家をねぐらとするが、家の四方には数十メートルの、赤松やカラ松、椹(サワラ)などがそびえ立っている。積雪や嵐で、倒木が起これば、私の家はぺしゃんこになる。何十年も存続が保障されている「住む」家とちがって、私の家は自然を主として生き永らえているといったほうが正確である。
一年半前、森にやってきたとき、あちこちに倒木があった。生活のためにも、家をつくるためにも、森を整備する必要があった。草を刈り、何十本もの倒木を片付け、腐った根っこを抜いた。家を建てる場所を確保するために生きている木も伐った。
森を整備する私は、自らの行いが自然の摂理に反する「不自然」な営みではないかと思い悩んでいた。倒木を片付けるにしても、一カ所にまとめるわけだが、半分地面に埋まっているようなものは、そのままにしておいたほうが、微生物に分解され早く自然に還っていく。引っ張り出して一カ所に積み上げれば森は綺麗になるが、土と接触しなくなった倒木は分解が遅くなる。
草を刈るのも、木を倒すのも、それが”自然的”か分からなかった。人間の手が加わることで、自然は歪となるのではないかと。草は大地に必要とされて生えているという。放置された人工林は、伐木したほうが森に光が差し込むが、そもそも人間の手が入る時点で何を「自然」とすればいいのか分からない。
私は、人間と自然を分断したところで、物事を考えていたのである。原生自然のような一次的自然を「自然」と考え、人間の手が加わった二次的自然は、相対的に価値が低いと見積もっていた。それが、そもそも物質観に侵されていたということである。
明治10年頃までは、日本に「自然」という言葉はなかったことは先日も書いた。われわれは、薪を集めるために、落ち葉を拾ったし、倒木も片付けた。結果として、里山は綺麗になりキノコや山菜がよく採れた。昔の里山は、何十種類も山菜が採れたという。そうして出来上がった「人為的自然」がわれわれの自然だったのだ。日本人は、人為的自然を劣ったものとして見ることも、原生自然を本来あるべき理想としても考えなかった。繰り返すが、そもそも「自然」という言葉すらなかったのだ。自然を敬い、生き物を敬った。天地の呼吸のなかに、われわれ人間は存在していた。生活の延長に、多様な生命が息づく、豊かな里山が生まれたのだ。多様な自然すべてに神がいたのだ。もっと鮮明に自覚することだ。己が自然の一部であると。永遠の命であると。
2025.1.13