- 生きることがめんどうくさいと感じている人
- 日々を惰性的に過ごすことに虚しさを感じる人
- 不満はないが、生きがいもない人
- かといって死ぬ理由もないから、ただ生きている人
⇒こんな方に向けて、文章を書いています。
「生きることは前向きであるべきだ」「人生は楽しくなければならない」そうした前提を、私たちは疑うことなく引き受けてきました。
しかし、冷静に考えてみれば、生きるという営みそのものが、そもそも面倒な構造を持っているとは思わないでしょうか。
われわれは自らの意志とは反して、この世界に投げ出されました。
食べる、働く、人と関わる、身体を維持する、責任を引き受ける。どれ一つをとっても、放っておいて勝手にすむものではありません。
宿題がめんどうだ。仕事がめんどうだ。人付き合いがめんどうだ。外に出るのがめんどうだ。
これはわれわれが怠惰だからでなく、生きることが本質的に自らの思いどおりにならない“不条理な営み”だからです。
にもかかわらず、私たちはいつの間にか、「生きることは楽しいもの」「前向きで、充実していて、意味があるべきもの」という物語を刷り込まれてきました。
その結果どうなるか。
生きることがめんどうくさいと感じた瞬間、「こんなふうに思ってしまう自分はおかしいのではないか」「もっと前向きにならなければならないのではないか」と、自分を責め始めてしまうのです。
しかし、ここで一度立ち止まって考えてみてください。
おかしいのは自分か、それとも世の中か?
生きることがめんどうくさいと感じてしまう理由は、われわれ個人の性格や努力の問題よりもずっと深い根のなかにあります。
前提を揺さぶってみれば、生きることがめんどうくさいと感じる感覚は、自分を怠け者だと証明するものではなく、むしろ、生を雑に扱えなくなった自分自身の生命に、救済を哀願しているように思えます。
何も考えず、何も感じず、ただ流されるだけで生きられるなら、「めんどうくさい」という感覚すら湧いてきません。
日々の惰性に虚しさを感じ、不満はないのに満たされず、生きがいがないことをどこかで問題だと感じている。
生きることがめんどうくさい。この感覚は弱さでありながら、現状に抗う強さでもあります。「このままではいけない」と告げる生命の叫びを感じやしませんか。
Contents
1. 生きることがめんどうくさいと感じる理由はどこにあるのか
- 「生きることがめんどうくさい」という感覚は怠惰や弱さではなく、
生きることが考えなくても成り立ってしまう時代構造の中で、生の実感と重さを失ったことから生じている。 - かつての人々は生の重さから目を逸らさず誠実に引き受けて生きており、
その実感の喪失こそが現代人の違和感の正体である。
生きることがめんどうくさいと感じてしまう理由は、怠けているからでも、心が弱いからでもありません。
むしろこの感覚が広がった背景には、
生きることが「考えなくても成り立つ時代」になってしまった、
という構造的な変化があります。
少し昔の日本人を想像してみてください。
たとえば、江戸時代の農村に生まれた二宮金次郎(尊徳)。
彼は貧しい家に生まれ、幼くして父を亡くし、家計は困窮しました。
十代になると伯父の家に預けられ、日中は畑仕事や家業に追われる毎日を送ります。
夜、勉強をしようと灯りを使うと、「百姓が学問などしてどうする」「灯は無駄だ」と叱られることもあったと言われています。
当時、灯油や薪は生活のためにあり、学びのために使う余裕など、どこにもありませんでした。
それでも金次郎は、昼は誰よりも働き、夜は許されたわずかな時間で学び続けました。
泥だらけの苦労にまみれながら、不条理な世界のなかを身一つでぶつかっていました。
やがて彼は、荒廃した農村や藩の財政を立て直す人物として後世に名を残しますが、
それは彼の心が特別に強かったというよりも、生きることに対して誠実だったからでしょう。
さて、かつては生きることが「抽象」ではなく、常に眼前としてあり、生の重さが逃れようのない現実として迫っていた時代でありました。
当時の暮らしは、今とは比べものにならないほど厳しかった。
食べるために働き、家族を養い、寒さや飢えや貧しさと隣り合わせで生きる。
今日明日食えるかが、常に問われていた。
そのような時代において、「生きることがめんどうくさい」と考える余裕は、ほとんどなかったでしょう。
生は抽象概念ではなく、身体と直結した実存そのものだったということです。
一方で、現代の私たちはどうか。
物質的には満たされ、生活は整い、明日の食事や寝る場所に困ることはほとんどありません。
生きるために必死で身体を動かさなくても、とりあえず生きられてしまう社会が出来上がりました。
結果、生きることは少しずつ実感を伴わないスクリーン上の人生になっていった。
生は抽象の中で軽くなり、実存から静かに切り離されていきました。
実際、世を見渡せば、人生の喜びを自分自身の生命の内ではなく、スクリーン上に見出すようになっている。
皮肉なことに、生きることが軽くなりすぎた結果、私たちは生の重さを感じられなくなった。
本来、生きるという、身体を使い、環境と向き合い、自分の思いどおりにならない不条理な世界に対して、
否応なく自己存在を引き受けさせられる営みの、その手ごたえが失われてしまった。
生きることが厳しすぎれば、人は死ぬ。
しかし、生きることが軽くなりすぎても、人は死ぬ。
この行き場のない感覚、実存と実感の欠如こそが、「生きることがめんどうくさい」と感じてしまう現代人の根底にあるものではないでしょうか。
生を雑に扱えなくなった生命が発している、静かな違和感なのです。
2. 生きることがめんどうくさいときに「死」を想う
- 人は生を実感できなくなったとき、「死」を想うことで失われた生の重さを取り戻そうとする。
- 日常に「死」を宿すことは、生を破壊する思想ではなく、生命を本来の燃焼へと引き戻すための、もっとも人間的な態度である。
生きることがめんどうくさくなったとき、人はしばしば「死」を想います。
それは決して、死にたいからではありません。生を感じられなくなっているからです。
病気になったとき、初めて健康な身体のありがたみが分かるように、
人間は「死」という極限を想定しなければ「生」を実感できない生き物なのだと私は思います。
二宮尊徳しかり、日本には武士道精神があり、武士道が日常に「死」を宿す役割を担っていました。
武士道とは、単に戦いの作法や忠義の思想ではありません。
いつ死んでも悔いがないように生きる、という覚悟を、日々の振る舞いの底に沈めておく精神のことをいったのです。
そのため、武士階級だけのものでもありませんでした。
百姓や商人まで、すべての日本人の根底に「死」として根づいていたものです。
毎日に「死」ある。今日も明日も、「死」とともに生きている。
だからこそ、言葉を慎み、仕事にぶつかり、恥を知り、親や国を思い、自らの与えられた境遇に生命を賭すことができた。
死が遠くにある未来の出来事ではなく、すぐ隣にある現実としてあったからこそ、生は死の輪郭のうちに自ずと浮かび上がった。
現代のように、死を想うことは、不吉なことでも、暗いことでもありませんでした。
むしろ、人間の歴史をみればその考え方のほうがむしろ自然なのです。
生きるとは、死ぬとは。
静かに生活に結びついた、そんな哲学こそが死生観であり、人間の尊厳と命を大切にする知恵、覚悟、倫理、そして人間の魂でした。
生きることがめんどうくさくなったとき、人が死を想うのは、
失われた「生の重さ」を、もう一度取り戻そうとする魂の反抗なのだと私は思う。
ゆえにわれわれに必要なのは、
生きることをめんどくさがって、生のうちに閉じこもるのではなく、
日常のなかに「死」の精神を打ち込むことに他なりません。
危険な思想でも、破滅的な態度でもありません。
むしろまったく逆で、消費に喘いでいた生命を、本来の形、生命燃焼へと向けていく、もっとも現実的で、もっとも人間的な態度です。
3 生きることがめんどくさいなら、「死」を引き受けて生きること
- 生きることがめんどうくさいという感覚は、生を捨てたい衝動ではなく、
生の重さを取り戻そうとする誠実な問いである。 - その答えは、自分の人生に一つの「死の哲学」を打ち立て、
娯楽的な生ではなく「死の重さ」を孕んだ思想と文化に身を晒して生きることにある。
ここまで見てきたように、「生きることがめんどうくさい」という感覚は、
生を放棄したい衝動ではありません。
むしろ、どう生きればいいのか分からなくなった誠実な魂が、
生の輪郭を取り戻そうとして発している問いでした。
では、どうすれば生は再び重さを取り戻すのか。
結論は、これまでもこれからも変わりません。
自己の人生に、一つの「死の哲学」を打ち立てること。
これしかありません。
古い思想書や宗教、哲学書が、何百年、何千年も読み継がれてきたのは、そこに「死に耐えるための思想」が刻まれているからです。
死の哲学は、生きる意味を問うことに始まり、どう死ぬかを問い続けています。
ここに一つの答えはない。
日本人なら武士道かもしれないし、あるいは西洋的なキリスト教の死生観に行き着くかもしれない。
歴史上に尊敬する人物があれば、その人間の哲学がそのまま自分に打ち立てられるかもしれない。
自分の人生に、一つの死の哲学を打ち立てること。
そこからしか、本当の意味で「自分を生きる」道は始まりません。
スクリーン上の「生」の娯楽に流れるのではなく、
読書や音楽、伝統文化といった「死」の重さに、
自分を鍛え直すつもりでぶつからなければならない。
厳しいかもしれないが、それがいつの時代にも行われていた、人間の生活である。
4 生きることがめんどくさいと感じた末に、森で暮らすようになった話
私は、消費文明から一度、距離を置くことにしました。
便利さや快楽は必ずしも悪徳ではありません。
しかし、絶え間のない刺激のうちで、本来あるべき生の重さが、軽薄な娯楽へと流されていく生活のなかでは、
自分の生命を到底救いきれないことを、本能が感じていたのでした。
そうして私は、二十代の終わり、自分のつくった森小屋に身を潜めて、半年弱の隠遁生活に入りました。
騒音から離れ、必要以上のものを持たず。
現実逃避でありながら、生と死をもう一度、同じ地平で引き受け直すための営みでした。
森の生活の中心にあったのは、消費ではなく対話でした。
トーマス・マン、ランボオ、ニーチェのような西洋文学と哲学書、
三島由紀夫や太宰治、戦前戦後の詩集と思想書に毎日ぶつかる日々でした。
読み、考え、沈黙し、また読む。
難解な書物では、一ページに一時間も二時間も対峙することがよくありました。
その繰り返しのなかで、私は少しずつ、自分なりの死の輪郭、
つまり人生を一本に貫く信念を形成していきました。
もちろん、今もまだ道半ばの身にはちがいありません。
おそらく死ぬまで、私は人間の生を問いつづけて生きるでしょう。
ただ一つ確かなのは、生きることがめんどくさいと感じていた昔の感覚はとうに消え去り、
消費され軽んじられていた生命は、確実に燃焼へと向かっていったということです。
生は依然として厳しく、不条理です。
しかし今は、その重さと不条理を抱えたまま、それを楽しんでいる。
生れたからには楽しまなけば、それこそが人生だと信ずるのです。
まとめ
- 「生きることがめんどうくさい」という感覚は、怠惰や弱さではなく、生の重さを失った時代構造から生じる誠実な違和感である
- 生きることが軽くなりすぎた現代では、実存の手ごたえが失われ、生きがいや意味を感じにくくなっている
- 人は生を実感できなくなったとき、「死」を想うことで失われた生の輪郭を取り戻そうとする
- 日常に「死」を宿す思想(死生観)は、生を否定するものではなく、生命を燃焼へと引き戻す人間的な態度である
- 生きることがめんどうくさいと感じたときに必要なのは、自分の人生に一つの「死の哲学」を打ち立てること
- 思想書や文学、宗教、伝統文化に身を晒すことは、生を軽薄な娯楽から引き戻し、自分を生きるための鍛錬となる
- 消費文明から距離を置き、生と死を引き受け直したとき、生命は再び重さと意味を取り戻し、燃焼を始める






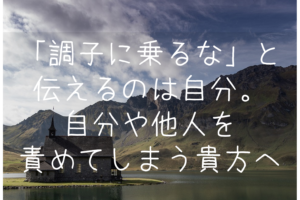

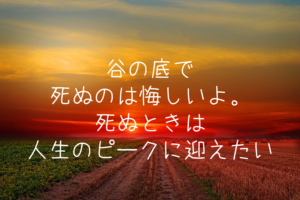
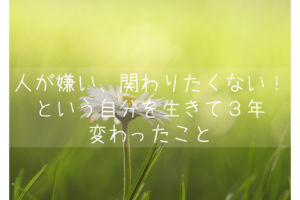

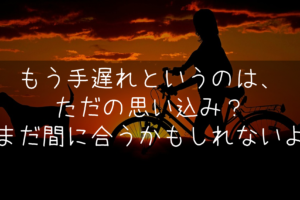


自分の気持ちに正直に生きることがどれだけ素晴らしいことか不思議と身体がほっとしてきたような感じになりました、
やりたいことがみえてないだけでこんなに苦しいとは、想像もつきませんでした、
今ある幸せに気づき、感謝することを忘れません。
へんなプライドは持たずに後悔しない人生にします。
自分の時間を大切にします!
ありがとうございました!