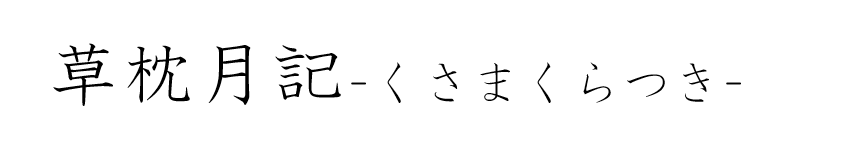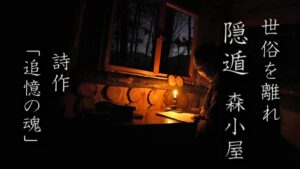人から借りたものはちゃんと返すことを子供のころに教わる。落し物は交番に届けることを子供のころに教わる。人様のものは人様のもとへ。神様のものは神様のもとへ。こうした信義誠実な国民性が、目に見えない恩の貸し借りの、文化の礎となっていると感じる。復讐もまたしかり。借りを返すという点ではエネルギーの法則にかなっている。それが平和的かどうかは別として、やられたことをやり返すのは人間的であり、程度によってはむしろ可愛げがある。
どんな赤子も両親の愛情を受けて育つ。赤子は笑い返すことしかできぬ。おれたちは現世に分け隔て産み落とされ、人様に借りを返すことで一体感を得た。一人前になると、生活や仕事をとおして、社会や国に貢献する。人様に借りを還せた(与えた)とき、愛を感じるのは、現象界を生んだ神の気持ちを汲むようである。人様に良くしてもらったのに、借りを返せないと最も情けない気持ちになる。借りを返すまでは死んでなるものかという気持ちになる。これも神の意図に反するからであろう。
大人になることと一人前になることは、同じ意味として使える。いつまでも与えてもらうことしか知らないのは子供である。これまで授かってきた恩の数々に、どうすれば報いることができるか、どうすれば借りを返せるかを想いつづけていれば、自分の人生が自分だけの人生ではないことが分かるようになり、うかうかしていられなくなる。
もし私のような青二才に、「立派」を語ることが許されるなら、きっとそれはこの世に多くの力を与えた人物をいうのだろう。所帯を持ち、子を持つことが、それだけで立派といえるのは、自分が両親から受けた愛情を、そっくりそのまま子孫に与えることができるからである。
そんな人間になれるよう、ひたすら耐え忍んで精進するのだ。
2024.10.4