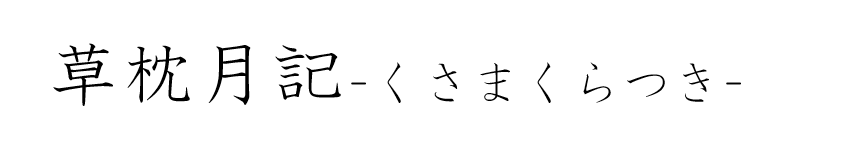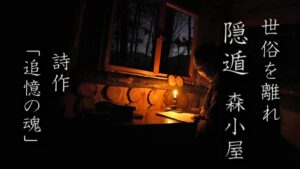江戸の頃まで、日本には”自然”という言葉は存在しなかった。山も川も、草木も空も、美しい自然は当たり前のように存在し、自己もまた自然の一部であった。”自然”という言葉は、文明開化によって”不自然”なもので分断されたことで生ずることになる。自然に還ることのない物質文明は、よく言えば、自然を”克服する”形で築かれたが、古くの日本人の感覚と照らし合わせれば、自己乖離が生じたといってもいい。
われわれの命は、単独で存在しているのではない。懐かしき故郷、遠い祖先から運ばれてきて、子や孫を通じて明日へ運ばれてゆく。命は時間を一直線に貫いている。それを形式として守護してものが大家族主義である。自然と分断され、家族は小さくなり、根源は不明瞭になる。われわれは何者かという問い以前に、自分が何者か、何のために生きているのかわからなくなる。脆弱な生を支えるためには、小さくなったエゴイズムを満たすしかない。虚無に蓋をしながらも、冷えた感覚を満たして生きるようになる。
ゴミを見れば気分が悪くなる。気持ちのいい人間などいやしない。掃除をすれば気持ちはいいが、やっていることの内実は、自分の目の届かぬ他所にゴミを押しのけて、棄てているだけである。分断の上に生活を築く以上、掃除もまた分断行為の一種にすぎない。自分の空間が綺麗になったことで満たされる、縮小したエゴイズムにすぎない。
感じるか。美しいものに触れようと悶えつづける魂を。その導きにしたがうことでしか、天に報いる道はないと知っている。何を語っても己の覚悟の問題でしかない。肉体の弱さ、文明との相克に敗れぬ強い力を、もって生きるしか道を知らぬ。力の哲学だ。自然から自ずと湧き生ずる、天地の力。
2024.1.7