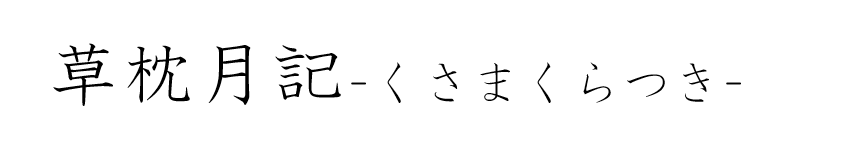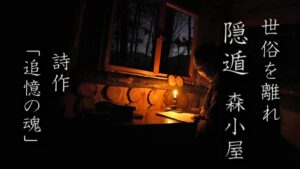長距離型の人間と、短距離型の人間では、エネルギーの出力方式が異なる。前者は安定したエネルギー出力を得意とし、後者はエネルギーを最大出力を得意とする。どちらも一長一短であるが、時と場合により、エネルギーの扱いを分けられる人間ほど、壁を乗り越えるのも容易となるように思える。例えば、マラソンでは、序盤に全力疾走すれば、先頭集団に入ることもできようが、後半はバテて後続に追い抜かれるのが関の山である。一方、同じエネルギー量を保有していたとしても、序盤から終盤までリズムよく走るほうが、記録は伸びるだろう。
エネルギーは保存される法則を思うと、こうした結果の違いは不思議である。だが、マラソンとはエネルギー効率を最大限に高める走法を用いた競技であり、全身の筋肉を駆使して、最高速度を出すこととは、目的がまるで違うのである。無論、これが100メートル走になれば、前者と後者の結果は逆転する。
私は元来、短距離型の人間である。高校テニスをしていたとき、シングルスでスタミナ切れとなり、足をつることで負けに転じた試合も多々あったが、ダブルスを専門にすることで欠点を補うことができた。ダブルスの守る範囲は、シングルスの半分となる。加えて、前衛が関与する分、試合展開はスピーディーになりやすく、スタミナがなくとも最大出力が高いことのほうがずっと優位である。
最近、畑で延々と働くようになって、今度は持久力が求められるようになる。これは先天的な性質と、長年の癖で、簡単に変えられるものでもなかろうが、私のような人間は、エネルギーの無駄がかなり多い。身体の細部に関心を向けてみると、使わなくてもよい筋肉まで力んでいることがよく分かった。それらを緩めるだけで、ずっと楽になるのだから不思議である。
食うことも寝ることも、命を燃やすためのエネルギーを授かる慣習である。生命を燃焼させるとは、毎日毎日、エネルギーをすべて使い果たすことであるが、どうせならこの授かりし力をうまく扱い、いい結果を求めたいものである。
2024.11.14