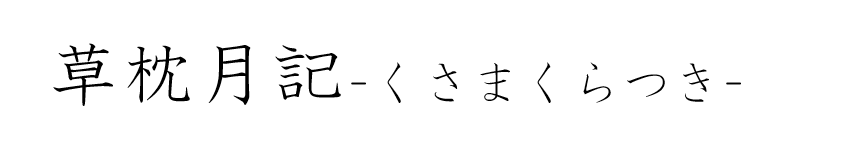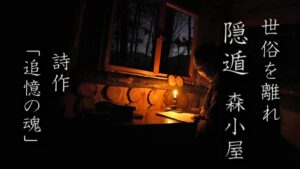母はなんて偉大な存在なんだろう。どれだけ偉大な愛情に支えられているだろう。それを胸に感ずるほど、孤独を厭わず真っすぐ生きねばならないという想いがこみ上げてくる。この身の養生を第一に心がけるのも、それがいちばんの孝行だからである。何でも好きな物を食って、好きに生活して、身体を悪くすることがどれほど親を悲しませることか。立派な職に就ければよし。温泉旅行をプレゼントすればよし。生活の足しになる金を入れればよし。そんな人並みな恩返しすら叶わぬこの落ちぶれた身の上では、母より授かったこの身体をいちばんに大切にし、毎日丈夫にたくましく働き、地道な暮らしのなかで力強く命を燃やしていくしか救いがない。母の愛情が偉大であるほど、この身は孤独を突き進まねばならぬ。強く、強く、生きねばならぬ。
***
思想によって救われた人間は、思想にすがることによって、一度は自己の生命を見失う宿命にあるのかもしれない。たとえば、ある哲学者の言葉に感銘を受けたとする。その言葉を俎上に載せて、自己の深みを潜考するのは結構である。だが、頭でっかちな人間ほど経験を不十分なまま省略し、ニーチェはああ言っただとか、キルケゴールはこう言っただとか、偉人たちの言葉を繋ぎ合わせて、自分の生き方のごとく講ずるようになる。まるで哲学パペットになってしまう。無論、この若輩者はニーチェやキルケゴールに学ぶ謙虚な態度を持たなければ、空論すら発せられない。だが一方で、迎合におちることのない自立した精神と、ぶつかり殴り合いに挑むような不遜で傲慢な態度が真に生きることには必要である。
最近あるビーガンの女性と話をした。彼女は人一倍繊細な心の持ち主で、動物が殺されるのが悲しくて苦しくて仕方がないと言う。一度は肉を食わないことにした。だがどうしても身体が肉を欲するようで結局肉を食うことにした。どうせ食べるなら感謝して食べようというのが彼女のたどり着いた結論ということで、貪り食うような真似はしないがバランスを見ながら適度に食うらしい。
私はビーガンのことは詳しくない。卵ならいいとか、四つ足が駄目だとか、流派も多岐に渡ると聞く。彼女の話を聞いたかぎりで感じたのは、まるで悲しみや苦しみから「倫理観」によって救われようとしていることである。「どうせ食べるなら感謝して」というのもまた一つの倫理であり文句のつけどころがない。だが、感謝によって罪悪感はなくなっても、動物を殺めた罪自体がなくなるわけではないのである。
ここに一つの目くらましがある。動物の犠牲の上に生きながらえている救いがたい現実のなか、「倫理」という家に閉じこもり、見せかけの安寧に自惚れている感がある。インチキ宗教も、頭でっかちな思想も、はたまた時代のヒューマニズムも、惰性的な習慣に身を窶すことも全部同じである。
荒々しい現実に眼を向けよ。自分を信ずればこそ、家から飛び出し曠野を歩むこと。それがこの世を真に生き切ることだと我が身に問うのである。おれは今一度「思想」の家を破り出て、孤独に歩むことを願うのである。